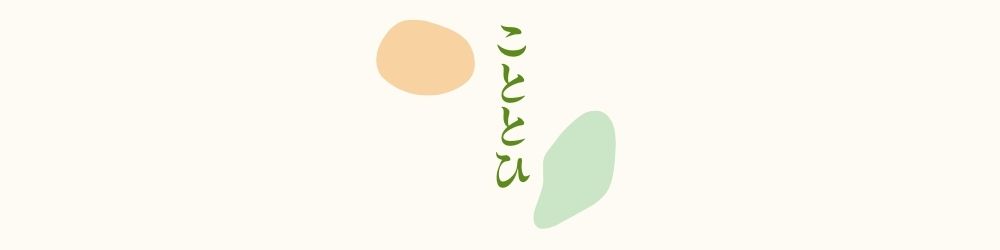
活動内容
 実践研究とは
実践研究とは
実践研究は知識や技術を社会で使えるようにするための方法論を確立することが実践研究です。証明された成果は社会実装の段階に移行します。このようにして社会で使われる手段は作られてゆきます。
現在の活動
 1.測定評価方法について
1.測定評価方法について
1. 子どもの読字、読解力
子どもが文字を読み、文章を理解できるようになる過程は非常に複雑です。読む力の発達が遅れる場合、その要因としては、視覚そのものに問題がある場合と、文字や文章の認識が困難であるといった高次機能的な問題がある場合とが考えられます。視覚の問題は視覚検査によって明らかにできますが、文字・文章の認識は脳の高次脳機能に関わるため、従来は簡単に測定・評価する方法がありませんでした。そこで私たちは、モバイル端末などを用いた簡便な生理機能測定によって、これらを定量的に評価できる方法の開発を進めています。
2. 心の動き(メンタルヘルス)
私たちは、ストレス状況や感情を定量的に測定する方法について研究しています。心理的ストレスの要因には、対人関係、家庭や職場の環境、学校や仕事における課題など、多様なものがあります。メンタルヘルスの問題を解決するためには、こうしたストレスの原因を個人の特性に基づいて明らかにすることが重要です。しかし、従来用いられてきたストレスチェックのアンケートによる評価では、その把握には限界がありました。そこで私たちは、アンケートを統計的に分析することで、より詳細に現状を評価できる仕組みの構築を進めています。
さらに、アンケート方式に加えて、日記やチャットに自由に書き込まれた文章を自然言語処理技術で分析し、ストレス状況を定量的に評価する研究も行っています。
3. 非認知能力
集中力や意欲、好奇心といった目に見えにくい能力は、従来の記述式試験では評価が困難です。このような能力は一般に非認知能力と呼ばれています。現行の学習指導要領においても「総合的な学習の時間」が重視されていますが、定量的に評価する方法が確立されていないため、教育現場に大きな負担となっています。私たちは、レポートなどに記述された文章を自然言語処理技術で分析することにより、考え方や好奇心、集中力などを測定する研究を進めています。さらに、モバイル端末を用いた簡便な生理機能測定によって、非認知能力を定量的に評価する方法の開発にも取り組んでいます。
4. 文章構成
行政機関や企業では、複雑な出来事を評価するために報告書が活用されています。報告書は書式が定められていても、記述内容は人によって異なり、集まった多数の報告書から共通する問題を読み取るには多大な労力が必要です。そこで私たちは、報告書に記載された情報を有効に活用できるよう、自然言語処理技術を用いて報告内容をスコア化し、統計的に処理可能な形で明確化する方法の研究を行っています。
子どもが文字を読み、文章を理解できるようになる過程は非常に複雑です。読む力の発達が遅れる場合、その要因としては、視覚そのものに問題がある場合と、文字や文章の認識が困難であるといった高次機能的な問題がある場合とが考えられます。視覚の問題は視覚検査によって明らかにできますが、文字・文章の認識は脳の高次脳機能に関わるため、従来は簡単に測定・評価する方法がありませんでした。そこで私たちは、モバイル端末などを用いた簡便な生理機能測定によって、これらを定量的に評価できる方法の開発を進めています。
2. 心の動き(メンタルヘルス)
私たちは、ストレス状況や感情を定量的に測定する方法について研究しています。心理的ストレスの要因には、対人関係、家庭や職場の環境、学校や仕事における課題など、多様なものがあります。メンタルヘルスの問題を解決するためには、こうしたストレスの原因を個人の特性に基づいて明らかにすることが重要です。しかし、従来用いられてきたストレスチェックのアンケートによる評価では、その把握には限界がありました。そこで私たちは、アンケートを統計的に分析することで、より詳細に現状を評価できる仕組みの構築を進めています。
さらに、アンケート方式に加えて、日記やチャットに自由に書き込まれた文章を自然言語処理技術で分析し、ストレス状況を定量的に評価する研究も行っています。
3. 非認知能力
集中力や意欲、好奇心といった目に見えにくい能力は、従来の記述式試験では評価が困難です。このような能力は一般に非認知能力と呼ばれています。現行の学習指導要領においても「総合的な学習の時間」が重視されていますが、定量的に評価する方法が確立されていないため、教育現場に大きな負担となっています。私たちは、レポートなどに記述された文章を自然言語処理技術で分析することにより、考え方や好奇心、集中力などを測定する研究を進めています。さらに、モバイル端末を用いた簡便な生理機能測定によって、非認知能力を定量的に評価する方法の開発にも取り組んでいます。
4. 文章構成
行政機関や企業では、複雑な出来事を評価するために報告書が活用されています。報告書は書式が定められていても、記述内容は人によって異なり、集まった多数の報告書から共通する問題を読み取るには多大な労力が必要です。そこで私たちは、報告書に記載された情報を有効に活用できるよう、自然言語処理技術を用いて報告内容をスコア化し、統計的に処理可能な形で明確化する方法の研究を行っています。
 2.介入方法について
2.介入方法について
1. 読み書きの苦手な子ども
子どもの学習の遅れの中でも、最も多いのは読み書きに関するものです。読み書きの遅れは国語だけでなく、他のすべての教科の学習にも影響を及ぼします。多重感覚アプローチ法は、読字や読解力の向上に有効であることが実証されています。この方法は、子ども同士が交互に教科書を音読し、視覚・聴覚に加えて、指で読んでいる箇所を示す触覚を組み合わせることで、複数の感覚入力を活用して学習する方法です。私たちは、この多重感覚アプローチをより多くの人が指導できるようにするため、講習会を開催しています。
子どもの学習の遅れの中でも、最も多いのは読み書きに関するものです。読み書きの遅れは国語だけでなく、他のすべての教科の学習にも影響を及ぼします。多重感覚アプローチ法は、読字や読解力の向上に有効であることが実証されています。この方法は、子ども同士が交互に教科書を音読し、視覚・聴覚に加えて、指で読んでいる箇所を示す触覚を組み合わせることで、複数の感覚入力を活用して学習する方法です。私たちは、この多重感覚アプローチをより多くの人が指導できるようにするため、講習会を開催しています。